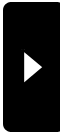2021年10月04日17:44
壁の内装材の話② 壁の調湿効果について≫
カテゴリー │家造りの役に立つお話│内装について
こんにちは。ツチヤ・フソウホーム 設計の石田です。
今日は内装材の『調湿性能』についてお話します。
『調湿性能』とは湿度が高い時(梅雨~夏)には湿気を吸い取り、湿度が低い時(冬)には湿気を放出する性能のことを言います。
湿気を吸い取る、若しくは通すだけでは調湿性能があるとは言えず、湿度の低い時には放出する必要があるという所がポイントです。
建築に使用する材料の場合、その材料が『調湿建材』と見なされるかどうかには判定基準があります。
繰り返される湿気の吸放出量が70g/㎡/24h以上。つまり1日に面積1㎡につき70g以上の水分を吸放出できるのか?
というのが一つの基準となっているのです。
それでは『調湿性能』を有する材料とはどんなものがあるのでしょうか。
住宅で『調湿』と訊いてまず真っ先に思いつくのは『塗り壁』ではないでしょうか。

四国化成 カタログより
一口に塗り壁と言ってもメーカーや使用する材料によっても効果に差があります。
今回は四国化成さんの珪藻モダンコートの数値を見てみます。

四国化成 カタログより
およそ90g/㎡/24h 90≻70なので調湿性能を有していると言えます。
続いて無垢材です。

当社 施工例 無垢の桐材を壁に貼った収納
無垢材のメリットとしてもよく『調湿性能』があげられています。
それでは無垢材の吸放出量はどれぐらいなのでしょうか?
無垢建材メーカーのウッドワンさんのホームページに無垢材の吸放出量が出ていたのでこの数値を使用させて頂きます。
無垢ピノアースのレギュラー塗装品 部位 羽目板の場合、面積10.92㎡で6時間で114.7gとのこと。
㎡/24hに変換したいので、(114.7/10.92/6)×24=42g
42<70で調湿性能は有していない。と判断するにはまだ早いです。
塗料をレギュラー塗装から自然塗料塗装に変えた場合の計算をします。
ただ、自然塗料の数値が何時間のものなのかの記載がないので少し回り道をします。
単板突板と比較した数値が自然塗料は8倍、レギュラー塗料は3倍とのことなので、自然塗料はレギュラー塗料よりも8/3倍吸放出量が多いはずです。つまり、
42×(8/3)=112g
112≻70なので調湿性能を有していると言えます。
ちなみにウッドワンさんのピノアースの樹種はパインです。
パインは無垢材の中でも調湿性能の高い(比重が小さい)樹種です。
比重の大きな広葉樹系の樹種では調湿効果が小さくなります。
また塗料によって調湿性能に差がでることもわかって頂けたと思います。
無垢床の熱伝導率の話でもお伝えしたように無垢材にウレタン塗装は無垢材の良さを消してしまいます。
続いてタイルの調湿性能です。
タイルと言っても一般的な磁器タイルではなく、多孔質セラミックタイル。代表的な商品としてはリクシルさんの『エコカラット』などがあります。

当社施工例 TV裏のアクセントにエコカラットを施工した例

リクシルエコカラット カタログより
エコカラットの吸放出量は24hで400gに近く、本日紹介した商品の中でもダントツです。
ただし高価であるため、大きな面積全てをエコカラットで施工するとなるとかなり資金が潤沢な人でないと難しいと思います。
続いては壁紙(クロス)の調湿性能です。
調湿性能を有した壁紙に珪藻土壁紙があります。

サンゲツ カタログより
こちらの吸放出量はおよそ90g/㎡/24hなので調湿性能を有していると言えます。
ただし、珪藻土壁紙は一般的なビニルクロスと比較して施工にかなり手間が掛かる為、高額になります。(一般的な壁紙の2倍以上)
また、クロスとクロスの重なった部分が目立ちやすいので仕上がりにこだわるのであればおススメしない商品となります。

サンゲツ カタログより
壁紙(クロス)には吸放湿機能付きのものもあります。
吸放湿量はおよそ43gと調湿機能を有しているとは言えませんが、一般的なビニルクロスとの差額がないので安価に吸放湿の機能を建物内全体に付与することが出来ます。
なぜ調湿壁紙と言わずに、吸放湿壁紙というのかこの記事を書いて分かりました。性能が足りていなかったんですね。
最後に内装材以外で調湿効果を得る方法をご紹介します。
その為に必要なのが、こちら

サンゲツ カタログより
通気性壁紙(クロス)です。一般的なビニルクロスよりも通気/透湿性が高いのが特徴です。
この特徴を利用します。
例えばクロスの下地のプラスターボードに吸放湿機能のあるものを使用します。

タイガーハイクリンボード カタログより
具体的な数値は出ていませんが、24hで500mlのペットボトル9本分(4.5L)の湿気を吸うとのこと。
珪藻土壁壁紙がコップ12杯分 およそ200ml×12杯 =2.4L ほどと推定。
その時の吸放湿量がおよそ90g/㎡/24hだったので、90×(4.5/2.4)=168g/㎡/24hの調湿効果が見込めるのではないかと思います。
断熱材にセルロースファイバーを選択するというのも調湿効果が期待できる方法となります。
当社でも屋根断熱にセルロースファイバーを採用して2階の天井クロスを通気性クロスにして調湿させる方法を標準としています。
様々な調湿効果のある材料を紹介してきました。
塗り壁を壁・天井の全体に採用した住宅の場合で夏の相対湿度を10%程度下げる効果が見込めるそうです。
それ単体で空調による除湿が不要になる訳ではありませんが、より少ない除湿力で建物内の除湿を賄うことができるようになるので省エネ化を計れます。
注意点としては調湿効果がある材料は透湿性を有しているので、どこかで『しっかりとした防湿対策をしないと壁体内結露のリスクが高まる』ということです。
調湿材料のカタログをみると結露対策になると書いてあるのを見かけますが、この場合の結露とは材料の表面結露のことだと思います。
※結露についての詳しい話は過去記事を参考
優先順位としては気密・断熱性能よりも下にはなりますが、調湿材料をうまく活用すれば高い質の室内環境を実現させることが出来ますよ。
今日は内装材の『調湿性能』についてお話します。
『調湿性能』とは湿度が高い時(梅雨~夏)には湿気を吸い取り、湿度が低い時(冬)には湿気を放出する性能のことを言います。
湿気を吸い取る、若しくは通すだけでは調湿性能があるとは言えず、湿度の低い時には放出する必要があるという所がポイントです。
建築に使用する材料の場合、その材料が『調湿建材』と見なされるかどうかには判定基準があります。
繰り返される湿気の吸放出量が70g/㎡/24h以上。つまり1日に面積1㎡につき70g以上の水分を吸放出できるのか?
というのが一つの基準となっているのです。
それでは『調湿性能』を有する材料とはどんなものがあるのでしょうか。
住宅で『調湿』と訊いてまず真っ先に思いつくのは『塗り壁』ではないでしょうか。

四国化成 カタログより
一口に塗り壁と言ってもメーカーや使用する材料によっても効果に差があります。
今回は四国化成さんの珪藻モダンコートの数値を見てみます。

四国化成 カタログより
およそ90g/㎡/24h 90≻70なので調湿性能を有していると言えます。
続いて無垢材です。

当社 施工例 無垢の桐材を壁に貼った収納
無垢材のメリットとしてもよく『調湿性能』があげられています。
それでは無垢材の吸放出量はどれぐらいなのでしょうか?
無垢建材メーカーのウッドワンさんのホームページに無垢材の吸放出量が出ていたのでこの数値を使用させて頂きます。
無垢ピノアースのレギュラー塗装品 部位 羽目板の場合、面積10.92㎡で6時間で114.7gとのこと。
㎡/24hに変換したいので、(114.7/10.92/6)×24=42g
42<70で調湿性能は有していない。と判断するにはまだ早いです。
塗料をレギュラー塗装から自然塗料塗装に変えた場合の計算をします。
ただ、自然塗料の数値が何時間のものなのかの記載がないので少し回り道をします。
単板突板と比較した数値が自然塗料は8倍、レギュラー塗料は3倍とのことなので、自然塗料はレギュラー塗料よりも8/3倍吸放出量が多いはずです。つまり、
42×(8/3)=112g
112≻70なので調湿性能を有していると言えます。
ちなみにウッドワンさんのピノアースの樹種はパインです。
パインは無垢材の中でも調湿性能の高い(比重が小さい)樹種です。
比重の大きな広葉樹系の樹種では調湿効果が小さくなります。
また塗料によって調湿性能に差がでることもわかって頂けたと思います。
無垢床の熱伝導率の話でもお伝えしたように無垢材にウレタン塗装は無垢材の良さを消してしまいます。
続いてタイルの調湿性能です。
タイルと言っても一般的な磁器タイルではなく、多孔質セラミックタイル。代表的な商品としてはリクシルさんの『エコカラット』などがあります。

当社施工例 TV裏のアクセントにエコカラットを施工した例

リクシルエコカラット カタログより
エコカラットの吸放出量は24hで400gに近く、本日紹介した商品の中でもダントツです。
ただし高価であるため、大きな面積全てをエコカラットで施工するとなるとかなり資金が潤沢な人でないと難しいと思います。
続いては壁紙(クロス)の調湿性能です。
調湿性能を有した壁紙に珪藻土壁紙があります。

サンゲツ カタログより
こちらの吸放出量はおよそ90g/㎡/24hなので調湿性能を有していると言えます。
ただし、珪藻土壁紙は一般的なビニルクロスと比較して施工にかなり手間が掛かる為、高額になります。(一般的な壁紙の2倍以上)
また、クロスとクロスの重なった部分が目立ちやすいので仕上がりにこだわるのであればおススメしない商品となります。

サンゲツ カタログより
壁紙(クロス)には吸放湿機能付きのものもあります。
吸放湿量はおよそ43gと調湿機能を有しているとは言えませんが、一般的なビニルクロスとの差額がないので安価に吸放湿の機能を建物内全体に付与することが出来ます。
なぜ調湿壁紙と言わずに、吸放湿壁紙というのかこの記事を書いて分かりました。性能が足りていなかったんですね。
最後に内装材以外で調湿効果を得る方法をご紹介します。
その為に必要なのが、こちら

サンゲツ カタログより
通気性壁紙(クロス)です。一般的なビニルクロスよりも通気/透湿性が高いのが特徴です。
この特徴を利用します。
例えばクロスの下地のプラスターボードに吸放湿機能のあるものを使用します。

タイガーハイクリンボード カタログより
具体的な数値は出ていませんが、24hで500mlのペットボトル9本分(4.5L)の湿気を吸うとのこと。
珪藻土壁壁紙がコップ12杯分 およそ200ml×12杯 =2.4L ほどと推定。
その時の吸放湿量がおよそ90g/㎡/24hだったので、90×(4.5/2.4)=168g/㎡/24hの調湿効果が見込めるのではないかと思います。
断熱材にセルロースファイバーを選択するというのも調湿効果が期待できる方法となります。
当社でも屋根断熱にセルロースファイバーを採用して2階の天井クロスを通気性クロスにして調湿させる方法を標準としています。
様々な調湿効果のある材料を紹介してきました。
塗り壁を壁・天井の全体に採用した住宅の場合で夏の相対湿度を10%程度下げる効果が見込めるそうです。
それ単体で空調による除湿が不要になる訳ではありませんが、より少ない除湿力で建物内の除湿を賄うことができるようになるので省エネ化を計れます。
注意点としては調湿効果がある材料は透湿性を有しているので、どこかで『しっかりとした防湿対策をしないと壁体内結露のリスクが高まる』ということです。
調湿材料のカタログをみると結露対策になると書いてあるのを見かけますが、この場合の結露とは材料の表面結露のことだと思います。
※結露についての詳しい話は過去記事を参考
優先順位としては気密・断熱性能よりも下にはなりますが、調湿材料をうまく活用すれば高い質の室内環境を実現させることが出来ますよ。