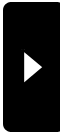2021年08月02日17:07
構造の話③ 耐力壁について 熊本地震から学ぶ≫
カテゴリー │家造りの役に立つお話│施工について(構造・気密・結露等)
こんにちは。ツチヤ・フソウホーム 設計の石田です。
今回は建物の耐震性能に大きく影響する『耐力壁』のお話です。
木造住宅は“土台”“柱”“梁”を組み合わせて建てられます。
それらをただ組み合わせただけでは上からの力(荷重)には強くても横からの力(地震・風)には弱い状態です。
地震や風などの水平力に抵抗する為に“筋交い”や“構造用面材”で補強した壁を『耐力壁』といいます。

耐力壁の強さは『壁倍率』という数値で表されます。
例えば、筋交いの厚さ45mm・幅90mmのもの1本で2倍
構造用合板の厚さ9mm以上のもので2.5倍等です。
筋交いと面材を組み合わせて4.5倍としたり大臣認定を取得した面材だと単体で4.0倍以上になるものもあります。
計算上で1つの耐力壁で5.0倍を超えた部分は評価されず、最大でも1か所で5.0倍とします。

耐震等級を上げる為には建物全体の壁倍率を上げる必要があります。
耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の強さと言われていますが、壁倍率を1.5倍にすれば満たされる訳ではありません。
実際に計算するとわかりますが、耐震等級1を耐震等級3にする為に必要な壁倍率は1.5倍程度ではまったく足りません。
およそ1.8倍程度の壁倍率が必要になります。
この耐力壁ですが、壁倍率を増やす為に闇雲に配置すると地震の力にうまく抵抗できなくなってしまいます。
まず耐力壁にしたい壁には1階の場合は基礎・土台・柱・梁、2階の場合は梁・柱・梁が必ず必要となります。
柱と柱の距離にも規定があります。
筋交いの場合は最小900mm、最大約2m 構造用面材の場合は最小600mm、最大約2mが必要です。
高さは筋交いの場合は最小約1.5m、最大3.185m 構造用面材の場合は最小約1.5m、最大4.5mです。
上記の幅・高さの規定を守らなければいくら筋交いや構造用面材を設けても耐力壁にはならないので注意が必要です。
耐力壁を配置する際の壁量計算では壁倍率と4分割法/偏芯率は最低限満たしています。
熊本地震で被害を受けた建物で問題となったものに『直下率』があります。

直下率は1階の柱や耐力壁の直上に2階の柱や耐力壁がある割合です。
これに関しては建築基準法での規定がないので最低限な壁量計算で基準を満たしていればどんなに直下率が悪い建物も建築できてしまいます。
最終的に許容応力度計算などを行えばその時点で是正はできますが、極端に直下率が悪い場合は間取りから変更する必要があるケースがほとんどだと思います。
1stプランの段階から構造計算をすることはほとんどないと思いますので、構造計算をした後でこの間取りだと耐震等級3は不可能といったことにならないように初めから直下率に注意して設計しておく必要があります。
当社では初期のプランから柱と耐力壁の直下率は最低でも60%を超えていることは確認します。
お客様の要望を満たした上で構造的にも安心な間取りを設計することは大切な職務だと考えています。
もう1つ熊本地震からの事例です。

日経ホームビルダーより
これは熊本地震で筋交いが破壊された様子です。
破壊された部分は柱~柱間の距離が1,820mmに筋交いが配置されている箇所です。
柱~柱間1,820mmに筋交いを2本入れた場合の壁倍率は8倍です。
大きな倍率の部分には地震力も大きく加わるので結果として破壊に繋がったのだと思います。
柱~柱間910mmを2箇所設けて8倍とする場合と比較すると長さは長くなるにしても筋交いが2本、柱が1本不要になります。
熊本地震の前であればコストダウン目的でこうした施工もありえました。(当社施工の物件でもありました。)
しかし、熊本地震での事例は専門誌で大きく取り上げられましたし、その後の講習などでも話題に上がっています。
故に今でもこうした耐力壁を使用しているとしたらそれはコストダウンではなく手抜き工事と言えると思います。
当社では外部分には筋交いは使用していませんが、内周部分には筋交いを使用しています。
いかに許容応力度計算をしていようと耐力壁の幅(柱~柱間の距離)は基本は910mm、最大でも1,365mmまでとしています。
構造的な失敗は実際に被災してみないとわかりません。
実際に被災された方が今後の住宅業界の為に事例を紹介してくれているのですから、この経験を無駄にする訳にはいきません。
(某ハウスメーカーはガードマンまで配置して立ち入り禁止措置をしたそうですが。。。)
最終的には許容応力度計算を行いますが、例えばお客様は自分でなんとなくプランをしてみたい場合は今日お話した直下率を意識してみて下さい。
構造的に無理のないプランになります。
基本は壁(柱~柱間)は910mm以上確保する。
1階と2階の窓の位置は合わせる。
これを意識するだけでかなり改善されます。
こうした知識をふまえた上でドライブしながら建物をみると外観だけでなく構造的にも色々な建物があって興味深いですよ。
次回も構造についてもう少しお話します。
それでは。皆様。
良い家を
今回は建物の耐震性能に大きく影響する『耐力壁』のお話です。
木造住宅は“土台”“柱”“梁”を組み合わせて建てられます。
それらをただ組み合わせただけでは上からの力(荷重)には強くても横からの力(地震・風)には弱い状態です。
地震や風などの水平力に抵抗する為に“筋交い”や“構造用面材”で補強した壁を『耐力壁』といいます。

耐力壁の強さは『壁倍率』という数値で表されます。
例えば、筋交いの厚さ45mm・幅90mmのもの1本で2倍
構造用合板の厚さ9mm以上のもので2.5倍等です。
筋交いと面材を組み合わせて4.5倍としたり大臣認定を取得した面材だと単体で4.0倍以上になるものもあります。
計算上で1つの耐力壁で5.0倍を超えた部分は評価されず、最大でも1か所で5.0倍とします。

耐震等級を上げる為には建物全体の壁倍率を上げる必要があります。
耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の強さと言われていますが、壁倍率を1.5倍にすれば満たされる訳ではありません。
実際に計算するとわかりますが、耐震等級1を耐震等級3にする為に必要な壁倍率は1.5倍程度ではまったく足りません。
およそ1.8倍程度の壁倍率が必要になります。
この耐力壁ですが、壁倍率を増やす為に闇雲に配置すると地震の力にうまく抵抗できなくなってしまいます。
まず耐力壁にしたい壁には1階の場合は基礎・土台・柱・梁、2階の場合は梁・柱・梁が必ず必要となります。
柱と柱の距離にも規定があります。
筋交いの場合は最小900mm、最大約2m 構造用面材の場合は最小600mm、最大約2mが必要です。
高さは筋交いの場合は最小約1.5m、最大3.185m 構造用面材の場合は最小約1.5m、最大4.5mです。
上記の幅・高さの規定を守らなければいくら筋交いや構造用面材を設けても耐力壁にはならないので注意が必要です。
耐力壁を配置する際の壁量計算では壁倍率と4分割法/偏芯率は最低限満たしています。
熊本地震で被害を受けた建物で問題となったものに『直下率』があります。

直下率は1階の柱や耐力壁の直上に2階の柱や耐力壁がある割合です。
これに関しては建築基準法での規定がないので最低限な壁量計算で基準を満たしていればどんなに直下率が悪い建物も建築できてしまいます。
最終的に許容応力度計算などを行えばその時点で是正はできますが、極端に直下率が悪い場合は間取りから変更する必要があるケースがほとんどだと思います。
1stプランの段階から構造計算をすることはほとんどないと思いますので、構造計算をした後でこの間取りだと耐震等級3は不可能といったことにならないように初めから直下率に注意して設計しておく必要があります。
当社では初期のプランから柱と耐力壁の直下率は最低でも60%を超えていることは確認します。
お客様の要望を満たした上で構造的にも安心な間取りを設計することは大切な職務だと考えています。
もう1つ熊本地震からの事例です。

日経ホームビルダーより
これは熊本地震で筋交いが破壊された様子です。
破壊された部分は柱~柱間の距離が1,820mmに筋交いが配置されている箇所です。
柱~柱間1,820mmに筋交いを2本入れた場合の壁倍率は8倍です。
大きな倍率の部分には地震力も大きく加わるので結果として破壊に繋がったのだと思います。
柱~柱間910mmを2箇所設けて8倍とする場合と比較すると長さは長くなるにしても筋交いが2本、柱が1本不要になります。
熊本地震の前であればコストダウン目的でこうした施工もありえました。(当社施工の物件でもありました。)
しかし、熊本地震での事例は専門誌で大きく取り上げられましたし、その後の講習などでも話題に上がっています。
故に今でもこうした耐力壁を使用しているとしたらそれはコストダウンではなく手抜き工事と言えると思います。
当社では外部分には筋交いは使用していませんが、内周部分には筋交いを使用しています。
いかに許容応力度計算をしていようと耐力壁の幅(柱~柱間の距離)は基本は910mm、最大でも1,365mmまでとしています。
構造的な失敗は実際に被災してみないとわかりません。
実際に被災された方が今後の住宅業界の為に事例を紹介してくれているのですから、この経験を無駄にする訳にはいきません。
(某ハウスメーカーはガードマンまで配置して立ち入り禁止措置をしたそうですが。。。)
最終的には許容応力度計算を行いますが、例えばお客様は自分でなんとなくプランをしてみたい場合は今日お話した直下率を意識してみて下さい。
構造的に無理のないプランになります。
基本は壁(柱~柱間)は910mm以上確保する。
1階と2階の窓の位置は合わせる。
これを意識するだけでかなり改善されます。
こうした知識をふまえた上でドライブしながら建物をみると外観だけでなく構造的にも色々な建物があって興味深いですよ。
次回も構造についてもう少しお話します。
それでは。皆様。
良い家を