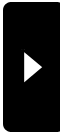2021年07月30日11:21
構造の話② 耐震等級3“相当”はピンキリです。≫
カテゴリー │家造りの役に立つお話│施工について(構造・気密・結露等)
こんにちは。ツチヤ・フソウホーム 設計の石田です。
前回は建物の耐震性能の基準となる『耐震等級』についてお話しました。
建築基準法ギリギリの耐震等級1ではなく耐震等級3で設計・施工を推奨する理由として『構造計算』の有無があります。

耐震等級を取得する際に必要な計算の有無
建築基準法の耐震等級1では地震に抵抗する『耐力壁』の位置や量を計算する壁量計算を行います。
しかしこの壁量計算では各階の壁量のバランスは計算しますが、1階と2階の耐力壁のバランスは考慮しません。
地震が起きた時、その力を建物の高い部分(屋根)から2階の壁、2階の床、1階の壁、基礎、地面と建物の低い部分に分散して逃がす必要があります。
1階と2階の耐力壁のバランスが悪いとうまく力が伝わらないので耐力壁が十分に機能しなくなってしまいます。
その力をうまく伝えてあげる為には2階の床や基礎の構造が重要になるのですが、耐震等級1の壁量計算ではどちらも計算はしません。
耐震等級1の場合、基礎や梁などは『スパン表』を基に設計されることが多いと思います。
この『スパン表』ですが耐震等級ごとに用意されている訳ではありませんので『スパン表』だけを満たそうとすると耐震等級1でも耐震等級3でも同じ基礎・梁で良いことになってしまいます。
さらに問題なのはこの『スパン表』すら守らなくても建築工事自体はできてしまうことです。
木造住宅を新築する為の確認申請には基礎や梁の構造図を添付する必要がないので極端に言うとものすごく手抜きな基礎や梁の設計でも建物は完成してしまうのです。
タイトルにある耐震等級3“相当”がピンキリだという理由がそこにあります。
①構造計算までやりながら申請費だけ削減するために耐震等級3取得までは至らない
実質 耐震等級3の建物もあれば
②壁量計算・直下率・耐力壁線・スパン表などを考慮した
完全な耐震等級3に結構近い“相当”もあり
③壁量だけは耐震等級3なみだけど1階・2階の配置はバラバラ、基礎や梁はケチってスカスカの
実質 耐震等級1以下 の耐震等級3“相当”が混在しているんです。
当社も以前は②の耐震等級3相当で建物を設計していましたが、現在はお客様に完全な安心をご提供する為、許容応力度計算による耐震等級3の取得を標準にしています。

構造塾 佐藤実氏 講義資料より
許容応力度計算は壁量だけではなく基礎や梁などの主要構造部にかかる様々な力に抵抗するための応力を計算します。
これに基づいた耐震等級3の取得が木造住宅の設計では最も信頼できるものだと思います。

完全な安心を得るのであれば許容応力度計算による耐震等級3
耐震等級3“相当”の場合は基礎・梁などを『スパン表』よりも大きくする。
1階2階の耐力壁の直下率にも注意する。
ということは最低でもやっておいた方が良いです。
次回は『耐力壁』や『直下率』について詳しくお話したいと思います。
それでは。また次回。
みなさま。良い家を
前回は建物の耐震性能の基準となる『耐震等級』についてお話しました。
建築基準法ギリギリの耐震等級1ではなく耐震等級3で設計・施工を推奨する理由として『構造計算』の有無があります。

耐震等級を取得する際に必要な計算の有無
建築基準法の耐震等級1では地震に抵抗する『耐力壁』の位置や量を計算する壁量計算を行います。
しかしこの壁量計算では各階の壁量のバランスは計算しますが、1階と2階の耐力壁のバランスは考慮しません。
地震が起きた時、その力を建物の高い部分(屋根)から2階の壁、2階の床、1階の壁、基礎、地面と建物の低い部分に分散して逃がす必要があります。
1階と2階の耐力壁のバランスが悪いとうまく力が伝わらないので耐力壁が十分に機能しなくなってしまいます。
その力をうまく伝えてあげる為には2階の床や基礎の構造が重要になるのですが、耐震等級1の壁量計算ではどちらも計算はしません。
耐震等級1の場合、基礎や梁などは『スパン表』を基に設計されることが多いと思います。
この『スパン表』ですが耐震等級ごとに用意されている訳ではありませんので『スパン表』だけを満たそうとすると耐震等級1でも耐震等級3でも同じ基礎・梁で良いことになってしまいます。
さらに問題なのはこの『スパン表』すら守らなくても建築工事自体はできてしまうことです。
木造住宅を新築する為の確認申請には基礎や梁の構造図を添付する必要がないので極端に言うとものすごく手抜きな基礎や梁の設計でも建物は完成してしまうのです。
タイトルにある耐震等級3“相当”がピンキリだという理由がそこにあります。
①構造計算までやりながら申請費だけ削減するために耐震等級3取得までは至らない
実質 耐震等級3の建物もあれば
②壁量計算・直下率・耐力壁線・スパン表などを考慮した
完全な耐震等級3に結構近い“相当”もあり
③壁量だけは耐震等級3なみだけど1階・2階の配置はバラバラ、基礎や梁はケチってスカスカの
実質 耐震等級1以下 の耐震等級3“相当”が混在しているんです。
当社も以前は②の耐震等級3相当で建物を設計していましたが、現在はお客様に完全な安心をご提供する為、許容応力度計算による耐震等級3の取得を標準にしています。

構造塾 佐藤実氏 講義資料より
許容応力度計算は壁量だけではなく基礎や梁などの主要構造部にかかる様々な力に抵抗するための応力を計算します。
これに基づいた耐震等級3の取得が木造住宅の設計では最も信頼できるものだと思います。

完全な安心を得るのであれば許容応力度計算による耐震等級3
耐震等級3“相当”の場合は基礎・梁などを『スパン表』よりも大きくする。
1階2階の耐力壁の直下率にも注意する。
ということは最低でもやっておいた方が良いです。
次回は『耐力壁』や『直下率』について詳しくお話したいと思います。
それでは。また次回。
みなさま。良い家を