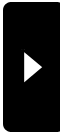2021年07月19日15:49
断熱の話⑬ 発砲プラスチック系断熱材の場合≫
カテゴリー │家造りの役に立つお話│断熱について
こんにちは。ツチヤ・フソウホーム 設計の石田です。
今回は発泡プラスチック系断熱材の施工についてお話します。
発泡プラスチック系断熱材を種類別に分類すると
・ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)
・押出法ポリスチレンフォーム(XPS)
・硬質ウレタンフォーム(PUF)
・フェノールフォーム(PF)
に分類できます。
細かい違いの説明は省略しますが、それぞれ原料だったり製法だったりが異なります。
簡単に言えば発泡スチロールなのですが、種類によって原料が違うということです。
現場発泡の硬質ウレタンフォームについては後日として、今回は板状の発砲プラスチック系断熱材についてお話します。
発泡プラスチック系断熱材の特徴としては
・断熱性能が高い
繊維系断熱材と比較して熱伝導率が低いものが大半です。
特にフェノールフォームや一部の硬質ウレタンフォームは断熱性能が高いです。
・吸湿性が小さい
繊維系断熱材と違い湿気を透し難いので、防湿層の設置が不要です。
・水に強い
繊維系断熱材と違い水に濡れても性能に変化がありません。
・熱に弱い
熱で溶ける。フェノールフォームは熱や火にも強いです。
・燃えた際有害なガスが発生する
製品にもよりますが、こうした性質のものが多くあります。
施工する時の注意点としては『隙間なく』施工することです。
断熱材自体は透湿性の低い素材ですが、隙間があれば当然隙間から漏気します。
ここでいう『隙間なく』とは単に木材にはめ込んだ状態のことをいうのではなく、何かしらの気密処理を施したもののことを言います。
例を見ていきます。

床の断熱材にビーズ法ポリエチレンフォームを施工した例①
上は当社で過去に施工した物件の写真です。
根太間に断熱材をはめ込んでいるのですが、通常□形状の根太と使用する所、凸形状のものを使用しています。
木材と断熱材の隙間をなくす為の工夫です。

床の断熱材にビーズ法ポリエチレンフォームを施工した例②
こちらも当社の過去の物件です。
根太工法の場合こうした間仕切り壁の部分に床下からの空気が入り易くなります。
それを防ぐ為に気流止め(きりゅうどめ)を施します。
気流止めは床・天井断熱の場合は床面・天井面で必須となります。

床の断熱材に押出法ポリスチレンフォームを施工した例
こちらは根太を使用しない剛床工法の物件です。
この状態では特に気密処理をしていません。

床の合板を張った後で、合板の継ぎ目に気密テープを施します。
柱廻りや床から出る配管・配線廻りも気密処理が必要です。

内基礎断熱にフェノールフォームを使用した例
断熱材の隙間となる基礎天端の部分に熱橋対策としてウレタンスプレー処理をしている。

外壁の充填断熱にフェノールフォームを使用した例
木下地を凹加工して挟み込んであるので隙間が生じない。
加工も工場で行っているので寸法の誤差がない。
木下地と柱の隙間は気密テープで処理をしている。

ネオマフォーム カタログより 外張り断熱にフェノールフォームを使用した例
木部を覆って施工できるので熱橋が無くなる。
継ぎ目に気密テープで処理をする。
固定方法はメーカー指定の工法を遵守する。
簡単な部分ですが、板状の発泡プラスチック系断熱材を施工する際の注意点についてお話しました。
次回は現場発泡ウレタン断熱材についてお話します。
それでは。また次回に。
皆様。良い家を
今回は発泡プラスチック系断熱材の施工についてお話します。
発泡プラスチック系断熱材を種類別に分類すると
・ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)
・押出法ポリスチレンフォーム(XPS)
・硬質ウレタンフォーム(PUF)
・フェノールフォーム(PF)
に分類できます。
細かい違いの説明は省略しますが、それぞれ原料だったり製法だったりが異なります。
簡単に言えば発泡スチロールなのですが、種類によって原料が違うということです。
現場発泡の硬質ウレタンフォームについては後日として、今回は板状の発砲プラスチック系断熱材についてお話します。
発泡プラスチック系断熱材の特徴としては
・断熱性能が高い
繊維系断熱材と比較して熱伝導率が低いものが大半です。
特にフェノールフォームや一部の硬質ウレタンフォームは断熱性能が高いです。
・吸湿性が小さい
繊維系断熱材と違い湿気を透し難いので、防湿層の設置が不要です。
・水に強い
繊維系断熱材と違い水に濡れても性能に変化がありません。
・熱に弱い
熱で溶ける。フェノールフォームは熱や火にも強いです。
・燃えた際有害なガスが発生する
製品にもよりますが、こうした性質のものが多くあります。
施工する時の注意点としては『隙間なく』施工することです。
断熱材自体は透湿性の低い素材ですが、隙間があれば当然隙間から漏気します。
ここでいう『隙間なく』とは単に木材にはめ込んだ状態のことをいうのではなく、何かしらの気密処理を施したもののことを言います。
例を見ていきます。

床の断熱材にビーズ法ポリエチレンフォームを施工した例①
上は当社で過去に施工した物件の写真です。
根太間に断熱材をはめ込んでいるのですが、通常□形状の根太と使用する所、凸形状のものを使用しています。
木材と断熱材の隙間をなくす為の工夫です。

床の断熱材にビーズ法ポリエチレンフォームを施工した例②
こちらも当社の過去の物件です。
根太工法の場合こうした間仕切り壁の部分に床下からの空気が入り易くなります。
それを防ぐ為に気流止め(きりゅうどめ)を施します。
気流止めは床・天井断熱の場合は床面・天井面で必須となります。
床の断熱材に押出法ポリスチレンフォームを施工した例
こちらは根太を使用しない剛床工法の物件です。
この状態では特に気密処理をしていません。
床の合板を張った後で、合板の継ぎ目に気密テープを施します。
柱廻りや床から出る配管・配線廻りも気密処理が必要です。

内基礎断熱にフェノールフォームを使用した例
断熱材の隙間となる基礎天端の部分に熱橋対策としてウレタンスプレー処理をしている。
外壁の充填断熱にフェノールフォームを使用した例
木下地を凹加工して挟み込んであるので隙間が生じない。
加工も工場で行っているので寸法の誤差がない。
木下地と柱の隙間は気密テープで処理をしている。

ネオマフォーム カタログより 外張り断熱にフェノールフォームを使用した例
木部を覆って施工できるので熱橋が無くなる。
継ぎ目に気密テープで処理をする。
固定方法はメーカー指定の工法を遵守する。
簡単な部分ですが、板状の発泡プラスチック系断熱材を施工する際の注意点についてお話しました。
次回は現場発泡ウレタン断熱材についてお話します。
それでは。また次回に。
皆様。良い家を